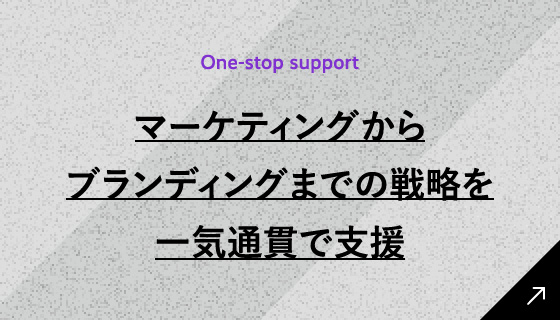- 運用
企業のホームページを失敗させる6つの方法

問い合わせが少ない、売上につながらないという失敗ホームページには、ほぼすべてに共通したポイントがあります。たまたま運悪く失敗しているのではなく、失敗は起こるべくして起きているのです。御社のサイトは失敗するために作ったようなサイトになっていませんか? チェックしてみましょう。
見た目をどうするかを優先する
失敗するホームページの多くは、見た目ばかりが優先されていて中身がおろそかです。どんな色にするか、どんな書体を使うか、どんな視覚効果を使うか、といった表現にばかりこだわる一方で、肝心の中身のほうは間に合わせ程度というのでは、訪問者から狙い通りの行動を引き出すことは不可能です。
企業活動の一環として製品やサービスの販売につなげるホームページを作るのであれば、まず準備すべきは「顧客がその製品やサービスを買うべき理由」であり、その理由が本当であると証明するための材料を集め、効果的な説明の流れを作ることです。こちらの狙った通りの行動を引き出す工夫なしに、売れるホームページは作れません。
ホームページから十分な問い合わせが得られていない理由は、ホームページの設計や運用において、訪問者から特定の行動を引き出すことに集中していないからです。ただ公開しているだけ、またはただ綺麗に作っただけで、狙った行動を引き出すための工夫や改善がされていないホームページでは、問い合わせがこなくても当然です。
狙った行動を引き出すために必要な個々の情報を、効果的な順番で配置すること、つまりホームページの構造を考えることが最初の仕事です。その構造をわかりやすく魅力的に伝え、訪問者が安心して行動できようにするために、見た目のデザインがあります。
まず、見出しでこちら側の約束(セールスポイント)を伝える。次に、その約束がどのようにして果たされるかを説明し、証拠を提示して、その商品がまったく謳い文句どおりであることを示す。それから価格と価値が釣り合うことを説明する。
肝心の中身もできていないうちから見た目についてあれこれ考え、中身を練り上げるところでは労力を惜しむというのが、失敗するホームページを作る最初のポイントです。そもそも順番が違うのです。まず中身を作り、次に見た目を作る、というのが正解です。
誰の役に立つのかを明確にしない
誰かの役に立つホームページを作るためには、その誰か、つまりダーゲットについて考え抜く必要があります。失敗するホームページに共通していることは、どんな目標を持ったどんな人が、どんな状況下で、どんな課題を抱えていて、どんな結果を望んでいるのか、という視点を欠いていることです。
- 優良な顧客になるのはどのような人物か
- 御社の製品やサービスを使いこなし、再購入し、他の人に推薦してくれるような優良顧客はどのような人物(または企業)か。それらの人々に共通する特長はあるか。
- 顧客が達成したい目標はどのようなものか
- 顧客は仕事や人生において何を達成しようとしているのか。目標を達成することでどんな結果を得たいのか。目標の達成を妨げている課題は何か。
- 顧客はどのような課題を抱えているのか
- 顧客は製品やサービスを使ってどんな課題をどう解決しているのか。その課題を解決することにどれほどの価値があるか。また解決しないことでどれほどの損害があるか。
- その課題はどんな状況下で発生しているのか
- 顧客はどのような人間関係の中でどのような立場にあるのか。仕事や人生におけるどんな転機を迎えているのか。どんなことに悩み、どんなことに痛みを感じているのか。
ホームページ制作にあたって、以上のようなことを明確にしているでしょうか? それらが訪問者に伝わるようになっているでしょうか? これらが伝わらなければ、どんなことが書いてあっても訪問者にとっては他人事です。ホームページが失敗するのは必然と言えるでしょう。
課題がどう解決するのかを示さない
御社のホームページの訪問者が一番に気にすることは「その製品やサービスを買うと自分はどんなふうに理想に近づくのか」ということです。それを明確に示さないホームページは、訪問者にとって見るべきものとはなりません。訪問者にとって見るべきものとは次のようなものです。
- 顧客のどんな課題をどう解決するのか
- 顧客のどんな欲求をどう満たすのか
- 顧客のどんな悩みをどう解消するのか
- その結果、顧客はどう理想に近づくのか
ところが失敗している多くのホームページに掲載されているメッセージは、自社の製品やサービスがいかに優れているか、いかに価格を抑えているか、またその実現のためにどれほど苦労しているか、などといったことが中心で、売り手目線に大きく偏っています。そのようなメッセージが訪問者の役に立つでしょうか?
ホームページに掲載すべきは、お客さまの課題であり、それを解決する方法であり、解決後の姿です。またお客さまの悩みであり、それを解消する方法であり、解消後の姿です。お客さまの欲求、その充足方法、そして満たされた姿です。
一方、多くの中小企業のホームページでは、自社やその製品やサービスがいかに優れているかという説明に終始しています。もちろん買ってもらうためには、優位性の説明は必要です。しかしそれは、お客様の願望をいかに充足するかという文脈に沿ったものである必要があります。
買い手の目線に立ち、買い手の課題解決に寄り添い、買い手の目標達成に道筋をつけるメッセージこそが、訪問者にとって役に立つメッセージです。売り手目線のメッセージは、訪問者にとっては他人事にすぎません。そうした役に立たないメッセージだけで構成すれば、役に立たないホームページが出来上がるだけです。
買うべき理由を明確に示さない
なぜ他の代替策ではなくその解決策を選ぶのか、また、なぜ他の販売者ではなく御社から買うのか、その理由が明確に示されていなければ、買い手としては選びようがありません。明確な「買うべき理由」を示していないホームページは素通りされるだけです。
「買うべき理由」というと、ほとんどの売り手からは高品質とか低価格のようなことが挙がりますが、これでは理由としては不足です。世界一高品質だとか、世界一低価格だというのであれば納得ですが、実際はそうではないからです。ほとんどの場合、品質や価格のほかに次のような要因がからんでいるはずです。
- 店舗や営業所が近い
- 店員や営業マンや社長との人間関係が良好である
- 深夜早朝や休日も営業しているなど営業時間が長い
- 小ロットでの注文に対応してくれる
- 製品の納期やサービスの提供スピードが早い
- 既存顧客が新しい顧客に熱心に推薦してくれる
- 状況に応じた提案がもらえる
- 商品知識や活用事例が豊富で知恵袋的な利用ができる
- 対応が親切丁寧で好感が持てる
- その顧客に合わせて製品やサービスパーソナライズできる
- サポートやアフターサービス、保証などが手厚い
顧客が選ぶ理由は多くの場合、品質や価格に加えて、上記のような理由の組み合わせになっているはずです。こうしたものを知るためには、思い込みを捨てて、実際の顧客、すでに御社から製品やサービスを購入した顧客の声を聞き、行動を観察することが最善です。
すでに御社から製品やサービスを購入した顧客は、どんなことに魅力を感じ、どんな理由で買ってくれたのでしょうか?「御社やその商品が既存客に選ばれた理由」が明確でなければ、そしてそれをきちんと示さなければ、新しい顧客は安心して選ぶことができません。ほかの役立つ会社を選ぶことになるでしょう。
目標をあいまいにする
運営企業側の目標があいまいなホームページは訪問者にとってもあいまいで、混乱するばかりでゴールにたどり着けません。まずは運営企業側が、どんな数字をどれだけ上げたいのかを明確にしておく必要があります。訪問者にとってわかりやすく役に立つホームページは、明確な目標設定から生まれます。
ホームページには明確で絞り込まれた目的やゴールが必要です。目的やゴールがあいまいなままでは、あいまいなデザインしか生まれず、中途半端な結果しか得られません。一方、絞り込まれた明確な目的やゴールがあれば、それを達成するための最適なデザインを導き出すことができ、より確実に結果を出していくことが可能になるのです。
ホームページのゴールを何に設定するかは、御社の営業活動の流れによって決まります。ゴールを資料請求に置くのか、見積もり依頼に置くのか、サンプル請求に置くのか、といったことは、御社の営業フローのどの部分にホームページを配置するかという重大事です。これを誤ればホームページは役に立たないものになります。
よくある間違いは、営業活動との連携を考慮せずに、ホームページのゴールを単に「お問い合わせ」などとしてしまうことです。こうなるとホームページは、御社の営業シナリオの1ステップ目として十分な機能を発揮できません。
また目標設定においては、どれだけの数字を上げるのかという数値目標を明確にすることが重要です。問い合わせを20%増加させたいという場合と、200%増加させたい場合では、ホームページの構成や集客施策がガラリと変わるためです。期待する数値目標があいまいなら、企画も設計もあいまいになり、得られる結果もそれなりです。
実際の顧客から学ばない
顧客から寄せられた質問やお問い合わせはホームページを改善するチャンスです。顧客が決断するために重要な情報のうち、現状のホームページに不足している情報、わかりにくい情報が明らかになるからです。これを改善し続けていくことで、ホームページは成長していきます。
当然のことですが、手を入れないホームページが成長することはありません。手をかけて育てていく必要があるのです。改善のヒントはあちこちにあります。とりわけ現場で顧客に接している営業マンや店員は、改善すべきことを把握していることが多いものです。
御社にも営業の勝ちパターンがあるでしょう。高い確率で契約をとりつけることができる見込み客や営業ステップのパターンです。そうした御社の営業活動における勝ちパターンをホームページに組み込みましょう。
ただ作っただけのホームページは、営業マンでいえば新人です。そこから手間と時間をかけて教育していかなければなりません。その教育こそがホームページ運用なのです。
訪問者の動きを記録したアクセス解析を使って改善ポイントを見つけていくこともできます。どのページが見られているか、どのページで離脱しているか、といったデータを元に、仮説を立て、改善し、結果を検証することで、ホームページは育ちます。
訪問者にとって十分にわかりやすく、不安を感じることなく購入や申し込みに進めるようにする第一歩が、社内での検証と修正・追記です。御社で扱う商品やサービスについて知識の少ない素人の訪問者の気持ちになって、不親切な説明があれば修正し、説明不足があれば追記します。
役立つホームページを作るスキルとは、つまり改善のスキルです。顧客の動きから仮説を立て、改善ポイントを実装し、顧客の行動の結果を検証する、という改善のプロセスを繰り返した経験によって、制作や運用のスキルが身につきます。作りっぱなしで改善しないというのでは、いつまでたっても成果を上げるスキルは身につきません。
不十分な結果しか生んでいないホームページは、ここまで述べてきた「企業のホームページを失敗させる6つの方法」に沿って作られます。御社のホームページはいかがでしょうか?